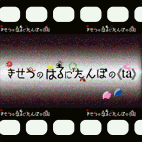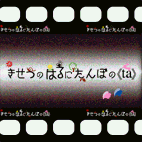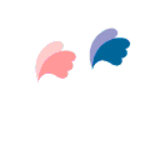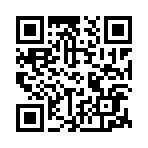2012年07月29日
高齢者との出会い
 子ども達が夏休みに入ると、有度地区青少年育成部の恒例行事となったサマーボランティアが始まります。
子ども達が夏休みに入ると、有度地区青少年育成部の恒例行事となったサマーボランティアが始まります。清水第七中学校の生徒を対象に、有度地区内にある2ケ所の高齢者施設を数日間のグループに分け、訪問します。
活動を始めて今年で23年目。
多くの子ども達がこの活動に参加してくれました。
 中学生である事が原則ですが、福祉の仕事に就きたいと、中学時代に3年間参加した後、福祉大学を卒業するまで参加し続けてくれた子どももいます。
中学生である事が原則ですが、福祉の仕事に就きたいと、中学時代に3年間参加した後、福祉大学を卒業するまで参加し続けてくれた子どももいます。活動をスタートさせた当初は、老人ホームという影のある響きにボランティアという名称をつけ、「いかにも!」というスタートだったのかも知れませんが、私たちが引き継いだ十数年前には介護保険が施行される時期とも重なり、その意味合いも変化することになりました。
 それまでは施設を訪問し、掃除を手伝ったり、車椅子の点検をするなど、施設側に対するお手伝いの要素を含んだいわゆるボランティア活動に徹していた感もありますが、核家族化も時代の主流となり、お爺さんお婆さんと同居していない子ども達も多く、人とのつながりを活動を通して体験する場に変わっていきました。
それまでは施設を訪問し、掃除を手伝ったり、車椅子の点検をするなど、施設側に対するお手伝いの要素を含んだいわゆるボランティア活動に徹していた感もありますが、核家族化も時代の主流となり、お爺さんお婆さんと同居していない子ども達も多く、人とのつながりを活動を通して体験する場に変わっていきました。 食事の介助や、入浴のお手伝いもさせていただきますが、基本は触れ合う事です。
食事の介助や、入浴のお手伝いもさせていただきますが、基本は触れ合う事です。上手に話せないお年寄りもいます。緊張のあまり、上手に話せない子どももいます。
両者が活動終了時点では握手を交わし、またおいで!また来るよ!なんて約束をしてくる様子こそ、この活動のポイントのひとつであると言えます。
 とかくボランティアといえば「イイコトをすること」みたいな印象がありますが、だから勝手に押し掛けていいわけはなく、当時開所マもなかった施設との綿密な打合せを重ね、その後新たに誕生した施設も含め、今のスタイルになるまでには幾度となく改善や方針の見直しなんかも行ってきました。
とかくボランティアといえば「イイコトをすること」みたいな印象がありますが、だから勝手に押し掛けていいわけはなく、当時開所マもなかった施設との綿密な打合せを重ね、その後新たに誕生した施設も含め、今のスタイルになるまでには幾度となく改善や方針の見直しなんかも行ってきました。決してキタナイ場所ではない施設訪問ですが、施設のアドバイスを受けながら、徹底した手洗いやお互いの「安全」を守るための決めごともしました。
 体験後の子ども達がつくる感想文集には「イイ顔」で写るお年寄りと子ども達の写真をたくさん掲載したいのですが、様々な事情で入所されているお年寄りの顔が写ってしまう事はNGだったり、編集段階で自主規制をしたりと、素晴らしい活動のすべてを紹介できないジレンマも現実です。
体験後の子ども達がつくる感想文集には「イイ顔」で写るお年寄りと子ども達の写真をたくさん掲載したいのですが、様々な事情で入所されているお年寄りの顔が写ってしまう事はNGだったり、編集段階で自主規制をしたりと、素晴らしい活動のすべてを紹介できないジレンマも現実です。 文集の中では、お年寄りから「ありがとう!」と言ってもらえた事を喜ぶ子ども達の文面が目立ちます。
文集の中では、お年寄りから「ありがとう!」と言ってもらえた事を喜ぶ子ども達の文面が目立ちます。いつからか、子ども達が始めたパフォーマンスの披露も、ギターを弾いたり、紙芝居を準備したり、空手のワザを披露したりと個性的なものもあり、施設側が準備するゲームでは、本当の孫と遊んでいるように見えるお年寄りの笑顔に単なるボランティア活動の域を越えた活動になったと実感します。
 数日間に渡り実施される活動には毎日数人の育成部員が引率同行します。
数日間に渡り実施される活動には毎日数人の育成部員が引率同行します。子ども達には夏休みでも、大人には平日なわけで、会社を休んで参加してくれる部員もいます。
施設のスタッフから「おじいちゃんコッチですよ!」なんて声をかけられちゃう育成部員も元気に参加してくれています。
また行きたい!と言う子ども達がいれば、施設と相談しながら何度も訪問させていただいた事もあります。
子ども達はお爺ちゃんやお婆ちゃんのあたたかさを実際に感じ、参加者としてではなく、この活動の本来の主旨を支えてくれています。
 学校に協力していただいて参加を希望する生徒を募りますが、先生が参加された事は一度もありません。私たちは他の地域活動においても先生を「先生としてではなく」ご招待するのですが、いろんな事情があるのでしょう。。。来ません。。。
学校に協力していただいて参加を希望する生徒を募りますが、先生が参加された事は一度もありません。私たちは他の地域活動においても先生を「先生としてではなく」ご招待するのですが、いろんな事情があるのでしょう。。。来ません。。。感想文集への入稿は子ども達には強制していません。原稿用紙を配るだけです。
完成した感想文集にはたくさんの生徒さんの「高齢者との出会い」が掲載されています。
先生にも入稿をお願いしてきましたが、ずいぶん前から掲載していません。
学校側は子どもたちの参加希望を募る際に、どんなキモチでご協力いただいているのか疑問に感じたこともありました。
私たちは参加したくない人を説得するエネルギーより、参加したくなる活動を目指しています。
昨日、明日からの訪問を前に、子ども達との事前説明会が実施されました。
今年はどんな出会いがあるのか楽しみです。
「動悸は何でもいい。活動する場所にいる事が大事ナンです。」
育成部OBのみなさんの意志は、子ども達と共に継承されています。
Posted by Nori at 14:03│Comments(0)
│子どもたち