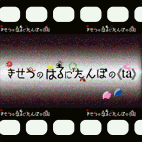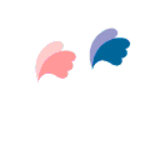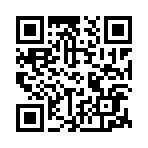2013年08月07日
夏休みの自由研究
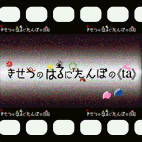 かなり若かりし頃。
かなり若かりし頃。待ち遠しい夏休みは、ナニかから開放される喜びと共に、積み上がるほどの宿題の山を、いかに無視し続ける事ができるのかという戦いでもありました。
ラジオ体操から始まる朝。
7時前に兄弟たちと帰宅すれば、「涼しいウチに宿題やっちゃいなさいよ!」と目を光らせる母の目を盗んでは、こっそり近くの広場に出掛けるのですが、当時は「10時までは外出してはイケナイ」とかいう学校からのお達しもあり、近所のオッサンに見つかれば、首根っこをつかまれて連れ戻されていました。
 広場の真ん中に建てられた「盆踊り」用のヤグラの裾に巻かれた紅白幕の中に隠れる事を思いつき、いざ実践してみれば、その中にはラジオ体操の出欠を記すハンコが隠されているのを発見すると、すぐさま首からブラ下げるヒモのついたラジオ体操カードを家から持ってきて、全部のマスに「出」と押し、堂々とサボルことを覚えるのですが、ラジオ体操の皆勤賞をもらいに行った時に、休みのはずの日曜日にまで「出」を押してしまっていたために、あっさりズルがバレ、逆に大目玉をもらったこともありました。
広場の真ん中に建てられた「盆踊り」用のヤグラの裾に巻かれた紅白幕の中に隠れる事を思いつき、いざ実践してみれば、その中にはラジオ体操の出欠を記すハンコが隠されているのを発見すると、すぐさま首からブラ下げるヒモのついたラジオ体操カードを家から持ってきて、全部のマスに「出」と押し、堂々とサボルことを覚えるのですが、ラジオ体操の皆勤賞をもらいに行った時に、休みのはずの日曜日にまで「出」を押してしまっていたために、あっさりズルがバレ、逆に大目玉をもらったこともありました。 木に登っては毛虫にさされたり、造園会社の庭に忍び込んでは、大きな蜂の反感を買い、イタイ目にあった事も夏休みの思い出と言えば思い出です。
木に登っては毛虫にさされたり、造園会社の庭に忍び込んでは、大きな蜂の反感を買い、イタイ目にあった事も夏休みの思い出と言えば思い出です。「地球が遊び場」だと、私たちが遊んでいた頃のような「子ども心」をそそる空間もあるのかないのか、すっかり景色の変わってしまった現在では、「転ばぬ先の杖」だらけで、過保護過ぎるほどに「アレもダメ!コレもダメ!」と神経質に「危険」をよけているウチに、子どもたちの好奇心も、そぎ落としてしまったのかも知れません。
 オフィスの隣にある学習塾も、朝から子どもたちが訪れ、勉学に励んでいます。
オフィスの隣にある学習塾も、朝から子どもたちが訪れ、勉学に励んでいます。教養も必要でしょうが、この世代だからこそ修得できる「生きるチカラ」のようなものを身につけるコトなく、数字や方程式を叩き込まれる子どもたちは、夏休みを楽しめているのか、それとも夏休みが同級生と差をつけるチャンス!と感じているのか、大して日焼けもしていない子どもたちと挨拶をしながら、ちょっと気の毒だったりします。
 夏休みの宿題で最も苦戦した「自由研究」は、アサガオやヘチマの成長を観察したり、山で採集してきた生き物の生態を百科事典を片手に調べたりもしました。
夏休みの宿題で最も苦戦した「自由研究」は、アサガオやヘチマの成長を観察したり、山で採集してきた生き物の生態を百科事典を片手に調べたりもしました。当時は昆虫たちも、昆虫らしかったのか、あちらこちらで活発に動くムシたちを容易く見つける事もでき、山のせせらぎの中にはイモリやタニシなんかを見つける事もできました。
 私が小学校3年生の時にテーマにした「アリの生態」では、エサを探し当てる能力や、高いところから落としても決して死なない理由なんかを子どもながらに調べてみたのですが、自身の何倍もの大きさや重さのあるエサを運ぶチカラがあるのに、なぜ大きなエサを運び込むはずの巣の入口はあんなに狭いのか・・・と、アリの巣をそーっと掘り返してみれば、ドコまでも続く「巣」の壮大さを追いかけているのがマドロッコしくなり、結局「爆竹」を巣に仕掛け、火をつけてみちゃうから大事な研究対象がコッパミジンになって、研究は終了となりましたと、中途半端な研究結果を夏休み明けに学校に持っていけば、案の定2学期のスタートは、廊下に正座をさせられていました。
私が小学校3年生の時にテーマにした「アリの生態」では、エサを探し当てる能力や、高いところから落としても決して死なない理由なんかを子どもながらに調べてみたのですが、自身の何倍もの大きさや重さのあるエサを運ぶチカラがあるのに、なぜ大きなエサを運び込むはずの巣の入口はあんなに狭いのか・・・と、アリの巣をそーっと掘り返してみれば、ドコまでも続く「巣」の壮大さを追いかけているのがマドロッコしくなり、結局「爆竹」を巣に仕掛け、火をつけてみちゃうから大事な研究対象がコッパミジンになって、研究は終了となりましたと、中途半端な研究結果を夏休み明けに学校に持っていけば、案の定2学期のスタートは、廊下に正座をさせられていました。 紙ヒコーキにカエルを乗せ、頼まれてもいないのに空中遊覧を経験させてやろうと誰かが言い出せば、もっと高い空を経験させようと言うアイデアも出て、ロケット花火に固定したカエルが夏空に打ち上がったまま、決して地上にカエルのままの姿で戻らない事も学びました。
紙ヒコーキにカエルを乗せ、頼まれてもいないのに空中遊覧を経験させてやろうと誰かが言い出せば、もっと高い空を経験させようと言うアイデアも出て、ロケット花火に固定したカエルが夏空に打ち上がったまま、決して地上にカエルのままの姿で戻らない事も学びました。黒いクルマを見つければ、「虫メガネ」で集めた太陽の光が塗装を焦がすくらいの温度になる事や、横断歩道を渡らないとクルマにひかれる事なんかも夏休みに学びました。
 ヤンチャ三昧、遊び三昧で迎える夏休みの最終日には、泣きながら積まれた宿題と向き合うことで得た教訓は、未だに活かされていません。。。
ヤンチャ三昧、遊び三昧で迎える夏休みの最終日には、泣きながら積まれた宿題と向き合うことで得た教訓は、未だに活かされていません。。。走り回る子どもたちの声が聞こえないのも「時代」なんでしょうか。
Posted by Nori at 10:15│Comments(0)
│独り言